令和7年度(2025年分)から、給与所得の状況によって、所得税がより軽減される可能性があります。働き方や扶養の考え方にも変化が生まれる可能性があります。年末調整の前に何がどう変わるのか、影響するのかしないのか確認しましょう!
- 税負担の軽減:給与所得者は年末調整で対応
- 給与所得控除の見直し:55万円の最低保障額が65万円に引き上げ
- 基礎控除の見直し:R7-8は段階的処置
- 特定親族特別控除の新設:居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満
- 扶養親族等の所得要件の見直し:給与所得控除・基礎控除の見直しに伴い
- 注意:住民税への影響
改正の背景
物価上昇に伴う「家計負担」の軽減や「働き控え」解消の観点から、税負担の緩和を目的とした改正。令和7年(2025年)分の所得から適用、給与所得者は年末調整で対応できる。
給与所得控除の見直し
最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。この給与所得控除は、給与所得者が年間で支出する必要経費をおおよそで見積り、収入から引いてくれるものになります。給与所得控除された収入が、給与所得(所得金額)になります。
表に示すように、給与が162万5000円以下の方は、改定後の給与所得控除額が10万円多くなるので、給与所得が10万円低くなります。同様に180万円の場合では、62万円なので3万円多くなります、190万円の場合では、65万円なので同額になります。一番恩恵を受けるのは、162万5000以下の方になります。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | その収入金額 × 40% − 10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | その収入金額 × 30% + 8万円 | |
給与の収入金額190万円超の場合、給与所得控除額に改正はありませんので、今までと同じ計算式が使われます。
基礎控除の見直し
2年間は所得金額に応じて段階的な処置が入っており、令和9年以降はこの処置がなくなります。この基礎控除は、先ほどの所得金額(給与の収入金額から給与所得控除されたもの)から控除され、課税額を計算する課税所得になります。
基礎控除と同じ所得控除には、生命保険料控除や社会保険料(毎月の給与から源泉徴収されたものなど)、iDeCoなどがあります。こちらも必要な支出なので、控除前の所得に対して、税を計算すると負担が多くなるため、控除後の金額に対して所得税を計算しようというのが課税所得になります。
| 合計所得金額 | 給与所得控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 令和7・8年分 | 令和9年分以後 | ||
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | ||
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | ||
| 655万円超 2350万円以下 | 58万円 | ||
合計所得金額2,350万円超の場合、基礎控除額に改正はありませんので、今までと同じ控除額が適応されます。
新設:「特定親族特別控除」
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従
者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
所得金額とは、先ほど説明した収入から給与所得控除された金額でした。つまり収入が123万円超188万円以下であれば良いということがわかります。これは190万円以下は、最低保証額の65万円が適応されるためです。
年末調整において「特定親族特別控除」の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給
与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、「扶養控除」の対象となるため、年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。
扶養親族等の所得要件の見直し
基礎控除の見直しに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が見直されました。基本的に10万円増えたことで、要件も10万円アップしています。また、給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。これにより、収入が10万円アップしても、収入が190万円以下であえれば給与所得控除が65万円なので、所得金額の増加分はプラマイ0になります。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超 133万円以下 | 58万円超 133万円以下 |
| 勤労学生 | 75万円以下 | 85万円以下 |
住民税は注意が必要?
今回の給与所得控除の見直しにより、所得金額が下がる人もいると思います。その方は、住民税も下がります。なぜなら、住民税は所得金額に対して、住民税における所得控除された金額に税率をかけて算出されるからです。
今回は、この住民税における所得控除(基礎控除、生命保険料控除や社会保険料など)は見直しがないため、収入が190万円を超える場合は、あまり影響はないかもしれません。
まとめ
- 給与収入が190万円以下:給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げ
- 所得金額2350万円以下:基礎控除が最低でも58万円に引き上げ
- 特定親族特別控除:新設、年末調整は書類提出あり
- 扶養親族等の所得要件:見直しに伴い、10万円見直し
- 住民税への影響は極小
このような改正により、自分にどれぐらい影響があるのか、結局どれぐらい税金が下がるのか、を理解するにはFP3級などの資格勉強がおすすめです。資格を取ることが目的ではなく、あくまで自分が気になる箇所を知っておくと良いと思います。(自分もそうしてます)
わかりやすく解説してくれるテキストも売っているので、自分に合ったのを購入してみるといいと思います。私は「みんなが欲しかったシリーズ」で勉強しました!
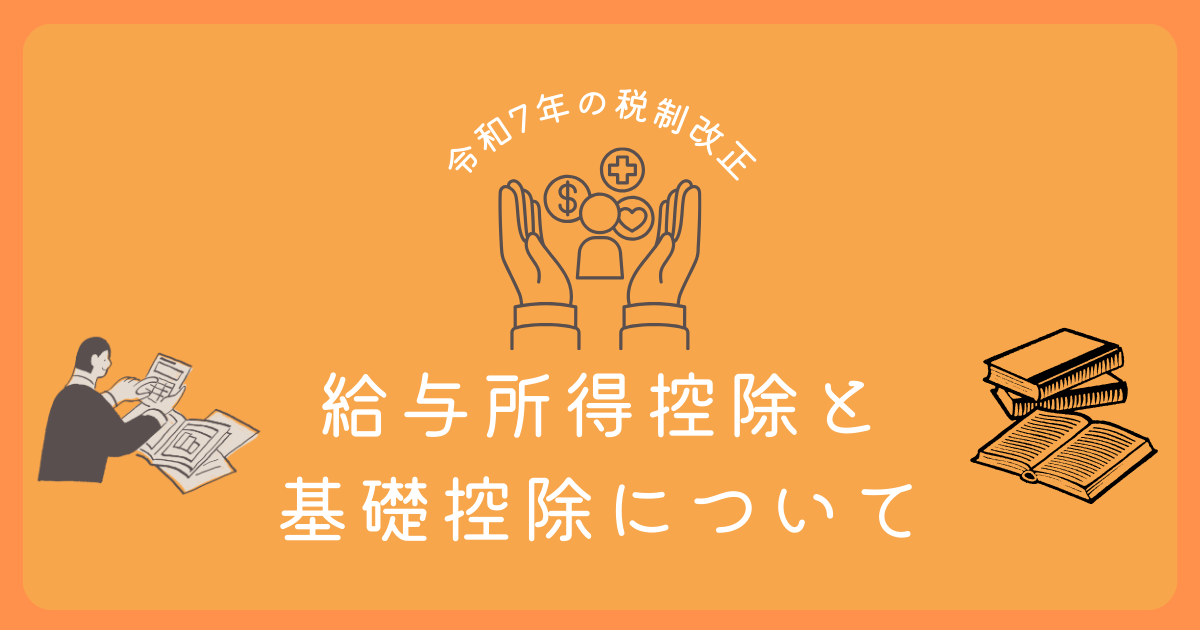
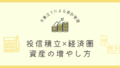

コメント